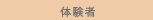「2006年6月にパンキャンジャパンという膵臓がんの患者会を立ち上げました。そちらの事務局でボランティアで仕事をさせていただいています。
妹が2004年の夏に膵臓がんと告知されて、アメリカの情報も一緒に探しました。そのときに情報ソースとしてロサンゼルスにこの本部があったので、そこに行っていろんな情報を集めることができました。活動内容を知るにしたがって、こういう団体が日本にあったら膵臓がんの患者さん、家族の方がたいへん助かるのではないかと思い、立ち上げる相談をしに行ったところ、先方の代表の方が快諾してくださったというのが経緯です。」
「実は妹のがんというのは、偶然見つかったのですね。彼女はその夏、この(左の鎖骨の)あたりにぽっくりと腫れがあり、リンパ節が腫れていたのです。微熱もあったので、何かおかしいとは感じたのですが、それが膵臓(からきている)ということは全然わからなくて。たまたま街医者に行ったところ『精密検査をしたほうがいい』ということで、精密検査をしてもらいました。そのときに甲状腺がんが見つかり、その知らせが私のところに来ました。私はそのとき京都に住んでいたのですが、知らせを聞いて甲状腺がんについてインターネットで調べました。命に別状のあるようながんではないとわかり、『よかったね』というメールを出しました。しかし、そのしこりの部分の生検をすると『原発はほかにある』という話になり、妹は慌ててA病院に入院して精密検査を受けたのです。そのときかかりつけの医者の話では、『たぶん子宮がんか卵巣がんではないか』という疑いがあったのですが、MRI検査を受けて、膵臓がんということがわかりました。妹が48歳のときです。」
「正直言いまして、妹も妹の主人も私も、膵臓がんがどういうがんだということは知らなかったのです。私もインターネットで調べますと、5年生存率というのが出てきて、これはかなりたいへんながんだということがわかりました。妹と義理の弟は、告知を受けたときに担当の先生に非常に深刻な顔をして『膵臓がんです。残念です』というようなことを言われたのですね。それでこれは結構たいへんながんかもしれないとは思ったのですが、実際どのくらいたいへんかということは当時すぐにはわかりませんでした。妹の主人はすぐに病院の地下の書店で本を買って読んで、『これはたいへんな病気かもしれない』と受け止めたのですね。私はインターネットで調べて情報をそのまま妹の携帯にメールを送って、『余命3ヵ月。すぐ動くように』ということを言ってしまったのです。それで(妹は)慌ててしまったという経緯があります。」
「彼女としてはなんとか自分が頑張って生き延びなければいけないという思いが、たぶん強かったのではないかと思うのです。最初のうち私は情報を流して、妹の主人も治療方法や病院の選択などの情報をいろいろ得ていたのですが、妹に対しては、なるべく治療に専念できるようにしたというのは事実ですね。それは私と妹の主人だけではなくて、母も叔母も妹の息子も同じ思いで、妹の周りにサポートチームを作ったという経緯があります。」
「病院でまず言われたのは、『セカンドオピニオンをどうされますか』ということで、当然、セカンドオピニオンはいろいろ聞きたいのでお願いして、病院を4つぐらい回りました。その中から迅速に対応できるところ、抗がん剤治療、放射線治療をかなりフォローできそうなところを選んで、そこにお願いしました。ただその準備をするにも時間がかかりますから、その間ずっと放っておくのではなく、最初にかかった病院にも『なるべく早い時期に抗がん剤治療が始められるように』とお願いしました。」
「まだ当時は、特にステージIVの転移された膵臓がんが見つかると、ほとんどの場合『もう助からないだろう』と医療者も思っている節があり、最初のA病院には緩和ケアもあるので、緩和ケア、それから抗がん剤をという話だったのですね。妹は『私は頑張りますから、ぜひ治療してください』と言ったのですが、それを受けて医療者の方が『わかりました、私も精一杯頑張ります』というような応答があればよかったのですが、どちらかというと控えめな回答しかなかったので、逆に不安感をつのらせたというところはあります。当時『がん難民』という言葉が流行していた時期で、膵臓がん患者は見捨てられてしまうのではないかという不安感があり、周りの者もたいへんな思いをしたというのは事実です。」